医療的ケアが必要な障害児とその家族の
QOLの向上を願って
医療的ケアが必要な障害児とその家族の QOLの向上を願って |
1.はじめに 養護学校に在籍する児童・生徒の障害が重度・重複化、多様化したと言われて久しい。とりわけ肢体不自由養護学校では、呼吸障害、摂食機能障害、排泄障害、体温調節障害等、健康管理に極めて配慮を要する児童・生徒が増えている。そして、その多くは、障害のために、痰の吸引、気管切開管理、経管栄養、導尿などいわゆる「医療的ケア」を日常的に必要としている。そして現在、この「医療的ケア」を必要とする児童・生徒について、学校教育での対応のあり方が大きな問題になっている。 事の発端は、1988(S63)年に東京都心身障害教育推進委員会が、「(医療的ケアが必要な)児童・生徒の教育措置は、原則として訪問学級とする」という方針を出したことによるが、それからすでに11年が経った。当時、東京や大阪など一部大都市圏の問題と言われていたが、今では、全国的な問題へと広がりをみせ、文部省も平成10年度から「特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究(1998~1999年)」を始めた。 私は、ちょうど1988年から医療的ケアが必要な生徒の教育に携わるようになり、これまで様々な取り組みを行ってきた。そこで今回、その実践と研究経過をまとめたので報告する。 2.医療的ケアの問題とは まず、この医療的ケアの問題について、その背景及び障害児教育の現場で何が問題になっているのかを紹介する。 (1)問題の背景と経過 重度の肢体不自由と重度の知的障害を併せ有するいわゆる重症心身障害児(以下「重症児」)について、以前は「最善の処遇は施設入所」と言われた時期があった。そして学校教育においては、多くの場合、就学免除・猶予の対象であった。 1979(S54)年の養護学校の義務制とともに、就学免除や就学猶予の児童・生徒は急速に減少した。義務制が始まった当時、訪問教育は教育保障の手段として大きな役割を担っていたと思われる(図1・省略)。 その後、「障害が重くても家庭で家族と共に生活する」という在宅療育の考えが一般的になり、それを支える簡便でコンパクトな医療機器の開発や医療技術の進歩があった。実際には、施設や病院のベッド数の不足、病院経営にとって長期入院が好まれない保険制度なども重症児の在宅を後押しする要因になっていた。ともかく、病院のNICU(新生児集中治療室)などで過ごしていた、日常的に医療的ケアが必要な子どもたちも、家庭で家族による介護を受けながら在宅生活をおくれるようになった。 これら医療的ケアが必要な子どもたちが、学齢になり、「教育も子どもの中で一緒に受けさせたい」という保護者の希望もあって、特に大都市圏の養護学校では通学籍として就学するようになった。そして、学校によっては、吸引や導尿などを保護者が日常的に行っている介護行為ととらえ、教職員が保護者や主治医から実技研修を受けて対応していた。 1988年、東京都教育委員会は、各学校での対応が異なることから、統一した見解が必要になり、東京都心身障害教育推進委員会の報告の中で、経管栄養や吸引、導尿などを「医療行為」とした上で、「(『医療行為』を必要とする児童・生徒の教育措置は)原則として訪問学級とする」という方針を出した。これが教育現場に大きな波紋をよんだ。また、その後、一部大都市圏の問題から全国的な課題に広がるにつれ、各地で同様の検討が行われて答申(表1・省略)が出されたが、この時の東京の方針は各地に大きな影響を与えた。 (2)何が問題になっているのか ①医療的ケアを教職員が実施することの法的問題 痰の吸引や経管栄養、導尿などは「医療行為」であり、医師や医師の指示を受けた看護婦(士)でない者、つまり学校教職員が行った場合、医師法第17条や保健婦助産婦看護婦法(保助看法)第31条に違反するおそれがあるという点である。 何を「医療行為」とするかは別として、これらの行為には、手技や衛生面での十分な配慮が必要であることも事実である。しかし、前述のように在宅医療・療育が普及する中で、医師の指導管理を受けながら保護者が日常的に行っている行為であり、医師にしか認められていない「絶対的医行為」ではなく、「相対的医行為」および「日常生活の中の介護行為」になっている。そういう意味で、現在は、痰の吸引や経管栄養、導尿などについては、「医療行為」ではなく、「医療的ケア」という言葉が使われるようになってきた。 法的な解釈については、弁護士による検討もいくつか発表されている。詳細は触れないが、医師だけに許される絶対的医行為ではないが、医師の管理下の置く必要はあるというグレイ・ゾーンであるために引き起きた問題である。 ②学校管理下での医療的ケア実施体制づくり 現在医療的ケアに取り組んでいる学校のほとんどは、「保護者の依頼・委託に基づいて、特定の子どもの特定の医療的ケアについて、特定の教職員が医師(指導医・校医・主治医など)に指導を受けて行う」という手続きで行っている。つまり特定の関係における対応であり、責任の所在を明らかにしたシステムが基本となっている。弁護士による法的な解釈でも、このような対応手続きであれば法的な問題はクリアーできるという見解である。 しかし、学校によっては、保護者の依頼に応じて、担任の熱意で行っている場合もみられる。そして、緊急時や事故が起きた場合に子ども自身の健康・生命と教師の身分を守るシステムがないために、教師、保護者双方が不安な中で過ごしている。 今、学校として「責任ある対応」を行うためのシステムづくりに各校が努力している。 ③医療的ケアが教育措置の基準になっていること 「(『医療行為』を必要とする児童・生徒の教育措置は)原則として訪問学級とする」という教育の措置基準になっている問題である。 教育の措置基準に、教育的なニーズより介護の有無に重点が置かれており、このため画一的な就学指導を行い問題になることもあった。例えば、肺の機能が低いために酸素療法が必要という以外は、健常のお子さんと変わりない子どもにも訪問教育を勧めるケースがあった。 また、通学籍の場合でも保護者の付き添いが義務づけられるケースが多く、家族に多大な負担をかけている問題がある。 以上、養護学校教育で問題になっている「医療的ケア」の概要を紹介した。次からは、この問題にどのように私自身が関わってきたか、その経過を紹介する。 3.教育実践及び研究の経過 1988~1994年 (1)医療的ケアが必要な生徒との出会い 私は、1988年4月に東京都立村山養護学校に着任し、高等部2年の担任で、最も障害の重い生徒の学習グループの指導担当になった。同じ学年には、教員に導尿してもらっている生徒がいたり、学習グループには、都内で初めてのケースと言われた気管切開をした生徒が在学していた。 ここでは生徒の一人、H君との関わりを中心に述べる。彼は、進行性の脳の障害で、小学校の心障学級の頃は会話も歩行もできていたが、徐々に会話も運動機能も低下して、知的障害養護学校、そして肢体不自由養護学校へと、その障害の進行と共に転校してきた。 H君が高等部2年の秋、いよいよ口から物が食べられなくなり、経管栄養になった。10月に学年の生徒、保護者、教員で行った河原での親睦会の中で、H君がカレーを食べている様子が、今でも鮮明に思い出される。お芋の天ぷらが好きな子だった。そして、これが私の見た彼の最後の口からの食事であった。 当時、導尿は教師が対応していたが、経管栄養については学校として取り組んだ経験がなかった。そのため、H君の経管栄養のために昼食時に保護者が来校するようになった。通常は、昼食時だけの付き添いであるが、校外行事や宿泊行事の際には同行していただいた。 高等部3年の時に行う3泊4日の修学旅行も全行程を保護者に同行していただいた。この学年の保護者はお互い仲が良く、この行事の期間に保護者だけで別に旅行に出かけていた。しかし、H君の保護者は修学旅行に同行したので、保護者の旅行には参加できなかった。当初、学年担任では、引率の中に医師(既に当時東京都では、修学旅行のみ医師の付き添いが認められていた)と学校看護婦がいるので、保護者の付添は必要ないと考え、またH君自身も含めて生徒たちにとって保護者が付き添っている状況は望ましくないと考えていた。しかし、校長や保健室スタッフ、保護者、主治医と検討の上、保護者には経管栄養の実施だけをお願いして付き添っていただいた。幸い、H君は、元気に全行程に参加できた。 次に当時、高等部卒業後、生徒と教師で企画して卒業旅行に出かけることが恒例になっていた。これは学校行事ではない全く私的な取り組みであった。この学年も同様に生徒と教師で卒業旅行を企画した。一方、保護者の方々も修学旅行の時と同じように保護者だけでの旅行を企画していた。 そこで、学年担任で検討し、保護者と相談した結果、H君の経管栄養を担任が実施することで、H君の保護者には他の保護者と一緒に旅行に出かけてもらおうと言うことになった。まず、主治医から経管栄養の研修を受けることになり、私が対応者に選ばれた。私は、昼食の時間は経管栄養の道具を持って、H君と一緒に学校に隣接する病院の外来に行き、主治医や看護婦に指導を受けながら経管栄養を行った。H君は、食事のたびにチューブを口から胃まで挿入する口腔ネラトン法という経管栄養であった。主治医は、この口腔ネラトン法を開発された方であり、丁寧に指導していただいた。私はH君と給食時間帯に毎日病院に通い、3週間ほど後に主治医から研修の終了と実施の許可をいただいた。 3月。卒業式を終えた次の日。卒業旅行に卒業生と担任、そしてボランティアとして知り合いの看護婦の参加も得て石和温泉へ出かけた。旅行中は、看護婦の手伝いをいただきながら私が経管栄養を行った。もちろんH君の保護者は、他の保護者と一緒に旅行を楽しむことができた。 この経験から、教師であっても医師や看護婦からしっかりと研修を受ければ、経管栄養でも「技術的に対応は可能」と感じた。この頃はまだ、医療的ケアの教育的な意義や学校としてどのように受けとめていけばよいのかということまでには考えが及ばず、なんとか保護者の介護の軽減をしたいという意識が強かった。 H君との出会いが、医療的ケアを初めて実施するきっかけであった。 (2)高等部教育相談と訪問教育 1988年に「(『医療行為』を必要とする児童・生徒の教育措置は)原則として訪問教育とする」という方針が出た一方で、実際には医療的ケアが必要な児童・生徒の入学は増えていた。問題になるのは新小学1年生と新高等部1年生であった。高等部は当時、訪問教育がないために、中学部の訪問教育であった気管切開や酸素吸入、吸引が必要な生徒が、高等部に「通学籍」で次々と入学してきた。東京都は、高等部希望者全員就学であり、「どんなに障害が重い子どもでも高等部教育を保障する」という理念の元、保護者、教師、教育行政などみんなで子どもたちの教育保障を進めてきた歴史があった。その上で、村山養護学校ではたとえ中学部で訪問籍であっても、生徒・保護者が希望すれば高等部入学を許可してきた。その頃私は、高等部で教育相談を担当していた。 1989年度の高等部入学相談は、大変難しい問題を抱えていた。前述のとおり、高等部は通学籍しかないために、訪問籍の生徒は中学部段階でスクーリングなど登校実績を作ってから高等部の入学相談に臨んでいた。しかし、その年の入学相談者の中で、隣接の重心施設で施設内訪問教育を受けていたK君は全く通学実績がなかった。K君は、経管栄養、気管切開、頻回な吸引、インスピロン(加湿を伴った酸素療法の機器)が必要であり、呼吸状態は大変不安定であった。登校実績がないことと生徒自身の健康状態の問題もあったが、教師の中には「重症児への教育なんて税金の無駄」と発言する者もいた。本校の管理職、主治医とも検討を重ね、「登校する場合は施設の看護婦が当分のあいだ同行する。更に教師が施設へ訪問してベッドサイド指導を行う。」など登校条件の設定と実質的な訪問指導を試みることで入学を認めた。 この高等部入学相談を通じて、重症児の教育保障の理解を職員間で深める必要が反省として出された。そこで、翌1990年に「障害児の後期中等教育の保障について ~その抱える問題点と重症児教育の理解のために~」という小冊子を教育相談担当者で作成し、高等部内で学習会を重ね、東京都の「高等部希望者全員就学」の意義を確認し合った。 K君が入学し、私が担任になった。施設の医師や看護婦スタッフの協力で、通常は気管切開をして人工呼吸器を使ってるK君は、週1回、学校へ施設の看護婦とともに登校して授業を受け、週2回は教師が病棟に行って授業を行う運用としての高等部の訪問教育を行った。 K君は楽器の音が好きで、手を持って一緒にピアノを弾くとガハハッと笑ってくれた。ギターの音も大好きであった。登校して同級生たちと劇遊びを行ったこともある。主治医の協力を得て校外行事にも参加できた。高等部に入学して、今までになかった様々な経験ができて、本人も保護者の方にも大変喜んでいただいた。しかし、残念なことにK君は、卒業間近の高等部3年の3学期のある朝に気管部からの大出血でこの世を去ってしまった。 K君との出会いは、障害の重い子どもたちの教育を保障してきた歴史を学ぶ機会を私に与え、教育実践を通して医療との連携の大切さを教えてくれた。そして私は、障害が重いなどの理由で学校に通うことが困難な児童・生徒へ教育を保障する訪問教育に深く関心を持つようになった。そこで、1991年度から在宅訪問教育を担当することになった。 (3)訪問教育に携わって 訪問教育の場合、個別の指導が基本であるため指導者として求められる知識や技術は多岐にわたる。一般的な障害者福祉制度や地域の福祉事情については、高等部に所属した3年間の進路指導を通じて理解していたが、保護者との関わりではカウンセリングも知っておく必要を感じた。それ以上に、児童・生徒の指導を行うための知識と技術を身につける必要を強く感じた。そこで摂食指導の研究会で勉強をしたり、同僚と計画して夏季休業中に重心施設のM愛育園で1週間の臨床研修を受けて、医療的な知識や介護技術を身につける努力をした。 また、1991年に一緒に訪問教育を始めた同僚と試行錯誤しながら、訪問教育という限定的な教育形態であっても充実した教育が保障できるようにと、指導内容の検討を繰り返しながら実践を行った。 (4)救急体制整備事業の取り組み 1990年に東京都教育委員会は、「医療行為を必要とする児童・生徒の教育措置等検討委員会」を設置した。その委員会が1991年3月に「医療行為を必要とする児童・生徒の教育のあり方について」を報告し、それを受けて都は、1992年度から「肢体不自由養護学校における医療体制整備事業」を策定した。 この「医療体制整備事業」の内容は、「①モデル校の指定・運営 ②研修事業の実施 ③医療との連携及び的確な研究の推進のための研究連絡協議会の設置・運営 ④医療に関する基礎知識に関する手引書の作成」であった。 私は、医療的ケアが必要な児童・生徒の教育実践を進めてきた経験から、この「医療体制整備事業」へ携わることになった。 ①モデル校 私の勤務していた東京都立村山養護学校がモデル校の指定を受け、私も校内の組織「医療体制整備委員会」の委員を務めた。モデル校としての研究は2年間で、その成果は1994年3月に「研究報告書 ~望ましい肢体不自由養護学校を目指して~」にまとめた。以来、本校の取り組みは全国的に知られるようになり、医療的ケアを教職員が実施する際の手続きや書類などは、多くの学校で参考にされている。 ②研修事業について 教育委員会が主催する医療的配慮に関する研修には、「専門研修」と「臨床研修」がある。 「専門研修」は、医師や理学療法士などを講師に、重度・重複障害児の病理や障害とその対応について、講義及び実技研修を行うものである。私も講師の一人として医療的配慮が必要な児童・生徒の指導事例などを紹介した。 「臨床研修」は、重症心身障害児施設等において、医療的配慮や介護技術など行う実践的研修である。この研修内容は、1991年に自主的に私たちがM愛育園で行った研修がベースになっている。 ③手引書の作成について 東京都教育委員会は、1992~1993年に医療的配慮に関する手引書作成委員会を設置した。委員会の1年次は、基礎編として呼吸障害や摂食機能障害、てんかん等病理や障害の基礎的知識とその対応方法をまとめた「基礎編」、2年次は指導事例を集めた「実践編」に取り組んだ。私は、2年次の「実践編」に参加して、呼吸障害のある子どもの事例をまとめた。 手引書は、1994年に「医療的配慮を要する児童・生徒の健康・安全の指導ハンドブック」として、東京都立肢体不自由養護学校の全教職員に貸与された。これを一部改定して1997年には日本肢体不自由児協会が市販するようになり、他県の教職員にも広く読まれるようになった。 (5)医療体制整備事業後の停滞 医療体制整備事業は、1992~1993年のモデル校の取り組みを受けて、1994年から事業名を「救急体制整備事業」に変更した上で、5か年計画で全都立肢体不自由養護学校に指導医を配置することになった。 しかし、折しもバブル後の税収不足、都の財政難から事業にかかる経費も厳しく抑えられた。更に、教育委員会が5か年で各校に順次指導医を配置することに対して、「校内が混乱する」などの理由で学校側から指定を受けることを拒む声もあり、この事業に対して外部からの援護はほとんどなかった。また教育委員会でも特に学務部が中心に取り組んだ事業であることから、庁内での不協和音も聞かれた。事業自体の継続が危ぶまれるようになった。 私はこのような事情を知り、この停滞した状況を少しでも好転させるためには、個人として何ができるか考えた。そこで、医療的ケアの問題は、それまで一部の養護学校の関係者の中で語られることが多かったが、多くの方にこの問題を知ってもらい、理解と協力を得ることが、この停滞状況を変える力になると考えた。そして、次の3つの方針を立てた。 ①当事者である保護者とのつながり ②理解ある医師とのつながり ③理解ある障害児教育の関係者とのつながり 4.教育実践及び研究の経過 1995~1999年 私は東京の取り組みの状況を憂え、この状況を変えるためには、外に理解者を広げること、いろんな人とつながることが必要と考えた。その取り組みをまとめる。 (1)保護者とのつながり 麻疹の後、ウイルスが体内に残って、ある日突然、脳で発症するSSPE(亜急性硬化性全脳炎)という難病がある。在宅訪問学級で担任したNさんは、この難病のために、気管切開、吸引、経管栄養を必要としていた。この病気の親の会で「SSPE青空の会」がある。私は、この会の賛助会員である。1995年の総会で医療的ケアの問題が話に出たことから、私は、「親の会としてもこの問題に取り組んで欲しい」という話をした。これが縁で、当時財団法人日本児童家庭文化協会事務局長の小林信秋氏(現「難病のこども支援全国ネットワーク」事務局長)や三宅捷太医師と連絡を取るようになった。 その頃、私は当事者である保護者の「医療的ケア問題」に関する意見を集める必要性を感じていたので、私が所属する研究団体「全国訪問教育研究会」を中心に日本児童家庭文化協会に集う難病の親の会の協力を得て、「医療的ケアに関する保護者アンケート」を実施した。その目的は、「医療的ケアを必要とする子どもの実態を調べるとともに、その保護者にこの問題に対する考えを聞き、よりよい教育的処遇と家庭支援のあり方を論議するための基礎資料づくり」であった。 アンケートの結果、「医療的ケアは親でも行えるほど技術的に簡単なのだから、子どもに一番身近な教師に医療的ケアを行って欲しい」という考えが一番多かったが、一方で「専門職である看護婦を配置して対応して欲しい」と医療スタッフを養護学校に配置して、より安全で快適な学校づくりを望む声が聞かれた。その他、このアンケートからは地域の医療や福祉などの社会的資源が貧しく、在宅療育の困難さを知ることができた。 1996年11月16日に財団法人日本児童家庭文化協会第17回こどもの難病シンポジウム「どーする医療的ケア」が実施された。全国的にこの問題が広まってきた時期で、全国から500名以上の参加者があった。この時、私はシンポジストの一人として指導医とともに東京の実情を紹介した。 以後も、様々な親の会の方や保護者の方と話をする機会を持つようになった。 (2)理解ある医師とのつながり 私は1991~1995年の5年間、在宅訪問学級の担任を務めた。私は同僚とともに、地域の中の医療・福祉関係者(保健婦、訪問看護婦、主治医、地域の医師、PT、OT、MSW、ヘルパーなど)と連携して訪問教育をすすめるように心掛けていた。 例えば、東京都の訪問看護事業の責任者である保健婦のもとへ、訪問教育について説明に行ったことがある。東京都は、衛生局母子保健課が窓口になって在宅重症児への訪問看護事業を展開している。私たちが児童・生徒宅へ訪問して授業を行っている時に、時々訪問看護婦と一緒になる時があった。「授業見学させて下さい」と言われ、看護婦にも一緒に授業に参加していただいたこともあった。逆に私たちが生徒の健康や介護について訪問看護婦に教えていただくこともあった。現場では、子どもと家庭を真ん中に、うまく連携が進んでいた。この連携を更に一歩進めようという意図で母子保健課の窓口に向かったのである。一通り訪問教育の説明を行い、「見ている子どもたちは同じなのだから、地域療育の仲間に入れて欲しい」という内容の話をした。その保健婦は「福祉と医療とは、常に連携を心掛けてきたけれど、教育については全く頭になかった。」と話し、その上で教育との連携の必要性をよく解していただいた。これを契機に、地域の医療と福祉サービスをコーディネイトする「保健福祉サービス調整会議」に学齢児の場合は、養護学校の教師にも参加を呼びかけていただけるようになった。また、訪問教育の教師と訪問看護婦合同の研修会も実施されるようになった。 ところで、東京都には訪問看護の他に医師の訪問健診という事業がある。担任した生徒の健診に同席した時、主治医の他に地域の医師会から派遣された開業医も参加されていた。この医師は、初めて気管切開をした重症児に接したようであった。私は、東京都教育委員会の研修会や手引書作成委員会、親の会などを通して多くの医師とつながりを持つことができたが、障害児医療に関係する医療従事者の中にも、医療的ケアが養護学校で大きな問題になっていることを知らない人が多いと言うことが分かった。そして、多くの医師にこの状況を知ってもらい、学校に手を貸してもらえるようにしたいと考えた。 そこで、重症心身障害研究会(現「日本重症心身障害学会」)の会誌(1996年V.21-№2)に「肢体不自由養護学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態」という論文を投稿し、医師に対して医療的ケアの実情の理解と学校への協力を求めた。 時期を同じくして、医療的ケアの問題に取り組んでいる「障害児(者)の療育・医療に携わる関東地区医師有志」の方たちが、関係の医師に理解を広げる取り組みを始めていた。厚生大臣への医療的ケアに関する要望書である(厚生省への正式な提出は1998年3月)。東京の窮状を理解しての取り組みである。 更に、1998年6月6日には、日本小児神経学会で公開シンポジウム「重度障害児の医療と生活支援~より良い在宅療育の実現を願って~」が行われた。私もシンポジストとして参加し、養護学校の児童・生徒の障害や医療的ケアの実態及び、医療的ケアの取り組みなどを紹介した。 理解ある医師によって学会や厚生省の研究班など組織としての検討・研究が始まっており、私も大変嬉しく思う。 (3)理解ある障害児教育の関係者とのつながり 1995年、東京の取り組みが終わるのではないかと危機感を持った私は、次に障害児教育関係者とのつながりを考えた。具体的には、肢体不自由教育に造詣の深い先生方に医療的ケアに対する考えを手紙でたずねることから始めた。そのほとんどの方から前向きに検討する必要のあるという返事をいただいた。特殊教育総合研究所に訪問し、私の話を聞いていただいた先生もいらした。 そのような人のつながりから、1997年5月に「医療と教育研究会(会長:村田茂氏 事務局代表:飯野順子氏)」が発足した。会の趣旨は、「新たな医療と教育の連携のあり方の研究を図る。特に、医療的ケアの必要な子どもの学校生活や卒業後の生活について研究する。」で、その活動内容は、 ①医療的ケアに関する情報交換をする。 ②医療的ケアに関する課題について理解・啓発を図る。 ③医療的ケアに関する課題について研究・研修する。 ④医療的ケアの必要な子どもの事例研究をとおして、学校生活や卒業後の生活等について研究する。 ⑤医療と教育の連携やネットワークについて考える。 である。この研究会は、1999年2月までに公開研究会を5回実施し、毎回100~200名ほどの参加者を得ている。参加者も保護者、養護学校教諭、教育委員会関係者、施設・医療関係者、研究者など多様である。 (4)一般の方へ理解を広げる取り組み この間、新聞記事やNHK教育の「こどもの療育相談」などマスメディアに医療的ケアの問題を取り上げていただくこともあった。 ある新聞記者が、「老人の介護問題を追っていたら、この医療的ケアの問題にぶつかった」と話していた。例えば脳卒中で重い意識障害と気管切開、経管栄養など医療的ケアが必要な状態で、病院をたらい回しにされたり、在宅介護で家族に多大な負担を強いている問題が起きている。医療的ケアが必要になったことで、在宅の重症児と同じ問題が持ち上がっているのである。 そこで、一般の人にもこの問題を知ってもらうために、個人でできることと考え、1999年1月にインターネットのホームページ「医療的ケアが必要な子どもと学校教育(http://member.nifty.ne.jp/kazu-page/)」を開いた。このホームページを見て興味を持っていただき、月刊誌「Yahoo! Internet Guide」1999年5月号のホームページ紹介「Yahoo! JAPAN Surfers' Picks」のコーナーで紹介していただいた。 全く障害児教育のことを知らない人たちから反響をいただいたことは、大変嬉しかった。 5.実践及び研究を振り返って 以上、私の医療的ケアに関する取り組みを簡単にまとめてみた。 医療的ケアが必要な子どもと出会った始めの頃は、教職員に医療的ケアの対応が可能なのかどうかということが、私の中心課題であった。それが、訪問教育の担任として家庭・地域へと出ていき、障害児とその家族を取り巻く様々な人との交流・協力を通して、地域療育問題という幅広い視点で捉えられるようになった。 「医療的ケアに関する保護者アンケート調査」の中の保護者の意見にも、 「医療技術の進歩で在宅も可能となったというが、家族の負担が重すぎると思うこともある。後々のケアが十分でないのなら救命などして欲しくない。生きて地獄を味わうような医療技術の進歩など少しも人間の幸福にはつながらないと思う。」とあった。現在の医療や福祉、そして教育も含めて在宅療育のまだまだ未整備な状況に対する痛切な批判である。 1998年から日常生活用具の給付品目に吸引器やネブライザーなどが入ったが、「やっと入ったのか」という思いである。それまで、保護者の方々はこれらを病院から貸与してもらったり、自費で購入していた。衛生材料も一部保険適用しているところもあるようだが、多くは自費で購入するしかない。いまだ在宅療育には、経済的な問題、レスパイトケアや日常の介護の問題、学校教育の問題、卒業後の問題など様々な問題がある。 医療的ケアの問題が、教育の現場で問題になって11年経つ。その間、訪問看護制度が老人から障害児者まで適用され、それまで医療の提供の場が病院や診療所に限られた時代から、居宅も含むようになった。そして来年には、介護保険がスタートするというように、医療・福祉の制度は大きく変わってきている。文部省も「特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究(1998~1999年)」を始めた。ここにきて医療的ケアの問題もやっと解決に向けてのスタート地点に立ったような気がする。 医療的ケアが必要な子どもたちが、安心で快適な学校生活を送れるようになるためは、どうしたらよいのか。就学前、学齢期、学校卒業後とライフステージを念頭に置いて、障害の重い子どもたちが、どうしたら地域社会の中でより豊かな人生(QOL)がおくれるようになるのか。私は、これからも人と人のつながりを大切にして、多くの人の知恵と協力を得ながら問題解決に取り組んでいこうと思う。 6.おわりに 以上、私が東京都立村山養護学校に勤務した11年間の主な取り組みである。 中学校理科の教師として採用されて、障害児教育については全く知識も技術も持ち合わせない私であった。その私が今日あるのも職場の同僚をはじめ、医療・福祉関係の方、そして多くの障害も持つ子どもたちと保護者の方々のおかげである。 重い障害のために、若くして亡くなっていった子どもたち。言葉はなくても、いろんなことを語ってくれた子どもたち。みんなに感謝したい。 【添付資料】 ①医療的配慮を要する児童・生徒の健康・安全ハンドブック ②医療的ケアに関する保護者アンケート調査報告 ③肢体不自由養護学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態,重症心身障害研究会誌,1996,V.21-№2. 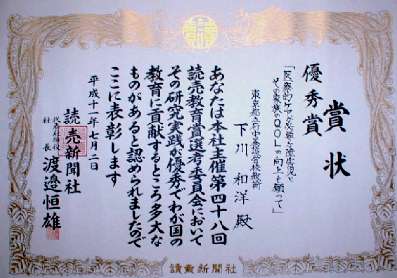  |